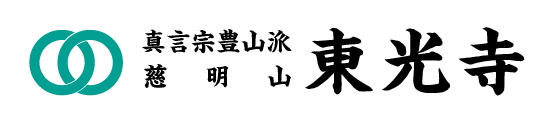天道念仏に
ついて
船橋の郷土芸能の
一つ「天道念仏」
此の寺には船橋の郷土芸能の一つともいうべき天道念仏というが行われて居った。これは此の寺と漁師町不動院、夏見薬王寺とだけに行われた梵天供(仏教守護の神梵天王を供養する修法)で、踊りの形は田楽踊りの一種と見られる。最近は此の寺本堂前公孫樹の下で行われ、これに就いて江戸名所図絵には次ぎの如く記してある。
天道念仏。船橋宮の内の東光寺及び漁師町の不動院、夏見の薬王寺等の境内に於て執行せり。毎歳二月十六日に始まり、同十八日に終わる。(昔は一七日の間執行せしが、今二夜三日とす)。堂前に土を以て壇を築き、竹を以て柱を設け、これを梵天と称し、其四方に四の門を開き四十八柄の神幣を建て、注連をひきはゆる等、皆悉く諸の仏天を表したり。内に大日如来の像を安じて本尊とし、百味の飲食を供養せり。其の詰衆の道俗は各一昼夜の間、六度づつ垢離して、浄衣を著し、白布を以て造る所の宝冠を頂き、三宝諸尊の御号を称えて敬礼し、六根懺悔の文を唱ふ。又、其間には彌陀の称号を唱へ、鉦太鼓を打鳴して、梵天の四方を右僥する事数回、昼間に間断なし。相伝ふ、住吉、弘法大師、出羽国湯殿山を始て踏分け給ひし頃、同国山形の東南、天道村といふ地に於てこれを開し給ふを興基として、こは五穀成就のための行事なりといひならはせり。
天道村というは今の山形県の北、山形県天童市のことであろう。この踊りもと天堂に行われたと見える
船橋市史 前編 昭和三十四年三月一日発行より抜粋